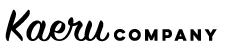2025.4.12 vol.557
店長教育とおもてなし力で
飲食店の人手不足を解決する
飲食店コンサルタントの結城です![]()
![]()
このブログは
「本当は手をかけたいけど、他の店舗に手がいっぱいで…」
「この赤字店舗、なんとかしたいけど店長もまだ頼れない…」
そんな飲食店オーナーさんのために書いています。
現場に入って、空気を読み、スタッフと話し
ときにはクレームを一緒に受けて、店長を育てて
その店舗が“ちゃんと回る現場”になるまで
寄り添って改善します。
「それって、もう右腕じゃん!」と
言われることも増えてきました。
ここでは、これまで500店舗以上の現場で得たノウハウを
わかりやすくリアルにお届けしていきます。
“まかせられる現場”をつくりたいオーナーさんへ。
ヒントが見つかるブログになることを願って
今日も書いています。
沖縄のお米の値段は日本一
さて、食材の高騰がひどい事に
なっていますね
私は沖縄と広島との
二拠点で生活をしていますが
沖縄での飲食店経営は
とっても大変です

今日本中どこも高騰している
「お米」の値段は
現在沖縄が日本一になっています

沖縄は輸送費がかかるので
本土からの食材は高く
代わりに沖縄で取れる食材は
とっっても安いです
これが沖縄のお弁当が
安く作れる理由のひとつでも
あると思います
知らないうちに赤字になってませんか?!
現場では日々変わる食材の
原価を常に抑えておく必要があります

個人店のように
毎日自分で食材を買いに行く機会がある
場合には値段に気づくと思いますが
ネットで決まった数字を入れるだけで
発注をしている場合
発注忘れを恐れるだけで
食材の値段の高騰には気づかない場合
売れば売るほどに
「赤字」になってしまっているかも

同じ人がいつもやっていると
ルーティンになっていて気づかない
こういう原価高騰が激しい時には
「売上が上がっても利益が減る」
という矛盾が起こりやすく
見過ごすと本当に怖いです。
定期的なチェックで防ぐ
現場で使える
「気づかないまま赤字になるのを防ぐ方法」を
いくつかご紹介します。
1. 「原価チェック日」を週1で設定する
ルーティン化された発注では変動に気づきにくいため
週1で「主要食材の原価チェック日」を作ります。

たとえば毎週水曜に
「最近高くなったものある?」と
発注業者に連絡 or 納品書を見てチェックするなど
ルーティンにしてしまう。
原価が5~10%上がったら要注意。
早期に気づけば即メニュー見直しできます。
2. 「重点食材リスト」を作る
メニューの中で
「原価率が高い or 使用頻度が高い食材」に絞って
重点管理リストを作成。
たとえば以下のように
スプレッドシートや
紙にまとめて管理するとわかりやすいです✨️
| 食材名 | 通常仕入単価 | 今週単価 | 増減率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 卵 | 200円/10個 | 250円 | +25% | 要注意、代替検討 |
| 牛肉 | 1,000円/kg | 1,050円 | +5% | 許容範囲 |
→ これがあると
誰が見ても「変化」に気づきやすくなり
店長初心者でも
オーナーさんと同じ目線で
話ができるようになります✨️

3. スタッフに「原価警察」を任命する
店長や発注担当者以外にも
「今週の高騰食材を見つける係」
=「原価警察」を任命する。
キッチンのアルバイトでも良くて
「あれ?最近これ高くない?」と感じたら
報告してもらう仕組みにします。

気づける目が増えると
チームで守る事ができるし
店長が忙しくっても
タスクオーバーになっていても
気づかない赤字を防ぐ事ができます
4. システム発注の「自動再計算」に頼らない
便利なシステムでも
価格変動を自動反映しないケースが多いです。

仕入価格が変わったら
「レシピの原価再計算」が必要ですが
それを毎回やらないと気づけません。
価格が変わったら
都度「主力商品の粗利率チェック」をする事で
売れば売るほどに赤字になる事は
防ぐ事ができます。
でも店長だけに任せると大変なので
いくつかの方法で
仕組みをつくって防いでいく事を
おすすめします✨️
5. 週次で「ベスト5メニューの粗利率」を確認
『売れてる=儲かってる』
ではありません。
売上TOP5メニューの
「原価÷売価=原価率」を毎週出して
変動していないか確認しましょう。
原価率が急に上がっていたら
価格改定や仕様変更も即検討していきます
ここのスピード感が大事です✨️

6. メニュー内で「高騰分を吸収できる調整メニュー」を持つ
原価が上がった時のために
「利益が出やすいメニュー」もあえて残しておき
全体でバランスを取ります。
例:出汁で引き立てる煮物
副菜、汁物など

1つずつのメニュー原価ではなく
全体原価率で調整します
ドリンクでも
ビール原価の高騰で調整できない所を
ハイボールなどの原価が安いメニューの
杯数を増やす事で利益減を防ぐ
そんな感じで
利益が出やすいメニューを
いくつも考えておくと良いですね。

良かったら参考にしてください。
■ 原価率チェックシート
■ 仕入れ原価チェックシート
ではまた明日
#もったいない赤字
#赤字店舗改善
#現場改善
#無駄の見える化
#クレームが多い店